●日本人
mtDNAとY染色体による現生人類の系統樹
日本人のY染色体亜型の系統は?
二重構造説 日本人は、日本人の起源論が好きである。実際、日本人の系統は単純ではなく、いまだに詳細がわかっていない。民族集団の系統関係と言語の系統関係がよく一致することから、言語の類似性から人種や民族の系統を探る試みが続けられてきた。言語学的にみると、韓国・朝鮮語と日本語は、いずもアルタイ諸語との関係が指摘されているが、…
ミトコンドリアは、核とは別に独自のDNAを持っています。このミトコンドリアDNAを使って、自分の祖先のルーツを調べる遺伝子検査がありますが、このページでは、人類がアフリカを旅立ち、日本に到着するまでの道のりを、このDNAから追いかけていきます。
Y染色体はミトコンドリアDNAと比べると塩基の数が3,000倍以上で、解析が容易ではありませんでしたが、最近ハプログループ分けがなされていて、ミトコンドリアDNA同様研究が進められています。
日本人の起源。ミトコンドリアDNAのデータが蓄積され、その分析から日本人の先祖が解明されつつある。
日本人の起源。ここでは、Y染色体亜型から、日本人の祖先の故郷を探す。
●人類~霊長目
最初の人類からホモ・サピエンスまで
分子時計を用いたヒト上科の系統樹
ヒト上科の系統樹
霊長目
霊長目
錐体視物質
脊椎動物はごく初期の段階から視物質の異なる4タイプの錐体視細胞(色つきの三角形で示す)を持っていたと考えられる。 哺乳類は進化の初期に,夜行性だったと考えられている。 薄明かりの元では,錐体視細胞はそれほど重要ではなかったために,4つのうち2タイプの錐体視細胞を失った。 対照的に鳥類やほとんどの爬虫類は,吸収波長の異なる4タイプの錐体視物質を持ち続けた。…今日の旧世界霊長類(アフリカやアジアのサル類と類人猿,ヒトを含む)に至る系統では,2つのうちの1つの視物質で,遺伝子重複とそれに続く突然変異がおき,これによって第3の錐体視細胞が”再生”された。
(日経サイエンス 2006年10月号)
(日経サイエンス 2006年10月号)
●哺乳綱
真獣類
げっ歯類
皆さんのお宅のネコさんに至る,猫2,500万年の進化の歴史をたどる; 5匹のイブがいたのまとめ
●鳥綱
パラベス;中生代の鳥類,デイノニコサウルス類
鳥類の分類は、古くから主に形態を指標に行なわれてきた。筋肉や骨、その他の構造の形態的な特徴を比較し、似ているものは進化の上でも近い関係にある、と考えて分類するのである。
●恐竜上目,主竜類
恐竜(双弓亜綱-竜盤目,鳥盤目)
竜盤目竜脚亜目
●爬虫綱
双弓類
有羊膜類
●脊椎動物門,魚類
硬骨魚類,棘鰭上目
http://www.pnas.org/content/110/31/12738.full
点線は,白亜紀と古第三紀のK/Pg境界。実は,棘鰭上目(条鰭類)も新生代になってから爆発的に多様化していた。
点線は,白亜紀と古第三紀のK/Pg境界。実は,棘鰭上目(条鰭類)も新生代になってから爆発的に多様化していた。
●節足動物門
ゲノム情報で昆虫の高次系統関係と分岐年代を解明(筑波大学)
http://zapzapjp.com/41806552.html
従来昆虫類は,デボン紀と呼ばれる今から約4億1600万年前から約3億5920万年前にあたる初期に誕生したと言われていました。今回の研究では分岐の時期がシルル紀より遡るオルドビス紀からカンブリア紀後期にあたることから、地上に植物や他の生物が進出したとほぼ同じ時代に、現在みられる昆虫の祖先が地上に進出したということになりそうです。
http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201411071600.html
従来昆虫類は,デボン紀と呼ばれる今から約4億1600万年前から約3億5920万年前にあたる初期に誕生したと言われていました。今回の研究では分岐の時期がシルル紀より遡るオルドビス紀からカンブリア紀後期にあたることから、地上に植物や他の生物が進出したとほぼ同じ時代に、現在みられる昆虫の祖先が地上に進出したということになりそうです。
http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201411071600.html
六脚類と甲殻類
汎甲殻亜門
六脚類(昆虫)
ハチ目
ミツバチ科
日本のオサムシの多くは、日本列島の中で独特の進化をとげてきた昆虫である。形態や交尾片を使って、種の分化・拡散についていくつかの説が出されているが、
●動物界
棘皮動物門
旧口動物
刺胞動物門
動物の分子系統樹
●緑色植物
麻とは -正しい認識をもとう-
植物学的に「麻」がつく植物を整理しておくと別記の「麻」の比較のようになる。このほかにも単子葉植物から双子葉植物までの7種もの植物が含まれる。たとえばマニラ麻はショウガ科、サイザル麻はユリ科であり、単子葉植物である。そのほかは双子葉植物だが、一年草から多年草、合弁科から離弁科までさまざまである。大麻(ヘンプ)はイラクサ科であり、花はごく地味なものである。これに対して亜麻は紫色の5弁のきわめて美しい花をつけるし、洋麻はアオイ科であり、アオイ、フヨウ、ハイビスカスなど美しい花をつける一群と近縁である。したがって「麻」とは「近縁な植物の総称」ではない。(麻布大学の麻展)
維管束植物
陸上植物
陸上植物の系統
陸上植物に近縁な緑藻類
被子植物の進化を大きな流れにして、植物のつくりを解説しています。APG分類体系を採用。他ではあまり見られない進化の系統図を掲載
花はどのようにしてできたか 植物の中で目立つのはやはり花だ。春になって花が咲いて初めて“あれ、こんなところに桜の木があったんだ”
葉緑体をもちながら動物のように動くミドリムシは、はたして植物なのか、動物なのか。高等植物は緑藻に属すシャジクモの仲間から進化してきた、と考えられているが、これは本当だろうか。
●真核生物
●生物全般
このページを閲覧することが出来ません。 設定でフレーム機能を使用していない場合は、使用できるようにしてください。 フレーム機能をサポートしていないブラウザの方は、 internet explorer4.5 以上のブラウザをインストールして下さい。
■サイト
Japanese / English 系統樹から NIES-MCC および KU-MACC に保存されている株を探すことができます。 また一部については各系統群の解説があります。 下の系統樹から探したい部分をクリック、もしくは上のボタンをクリックしてください。 注:各系統樹は分子系統学的情報をもとに確からしい部分を抽出して作成していますが、絶対的なものではありません。また各保存施設の同定もしくは…
Tree of Life 生命の樹 Tree of Life Short cut 生命の樹:ショートカット:目的の系統と分類群はこちらから 生命の樹: すべての生物には血縁関係があります。その関係はちょうど家系図のようなもので、枝分かれした図で表わすことができます。それをダーウィンは生命の樹と呼びました(「種の起源」上下 岩波文庫 を参考のこと)。 生命の樹についてもう少し詳しく→ このコンテン…
多様な切り口から生命誌を考えてきた季刊「生命誌」は、20年間で80号、記事数は700を超えます。この蓄積を俯瞰し、対談、研究、研究者紹介で語られた内容や言葉を相互に関係づけました。例として、「ゲノム」と「生活」をキーワードに持つ記事に注目したところ、ゲノムから複雑系を通してゲーテへ、生活から風土を通って真核生物へという思いがけない展開が見えました。「生きている」を見つめ、そこからどう「生きる」か…
系統樹ハンターの狩猟記録
系統樹ウェブ曼荼羅 第12回 時空的に変遷するオブジェクトの系統樹:総括として」 第11回 「文化構築物としての写本の系統と進化」 第10回 「人間の綱:血のつながりを視覚化する図像的伝統」 第9回 「新大陸先住民の知識体系としての生命の樹」 第8回 家系図の図像学:生命の樹と唐草模様 第7回 祖先の蔭に護られて:系統樹二千年の歴史をさかのぼる 第6回 円から球へ:高次元系統樹を描く 第5回 鎖…
Tree of Life Web Project Explore the Tree of Life Browse the Site Root of the Tree Popular Pages Sample Pages Recent Additions Random Page Treehouses Images, Movies,… News Darwin 200: the celebrati…
UCMP Phylogeny Wing : The Phylogeny of Life The ancestor/descendant relationships which connect all organisms that have ever lived. The Biosphere: Life on Earth Life! It’s everywhere on Earth; you ca…
Home page for Palaeos: all about the evolutionary history of life on Earth through geological time.
◦古いもの
ヘッケル『人類進化論』(1874年初版)
その他
情報技術の進化
https://matome.naver.jp/odai/2143082848007038901
2018年01月09日

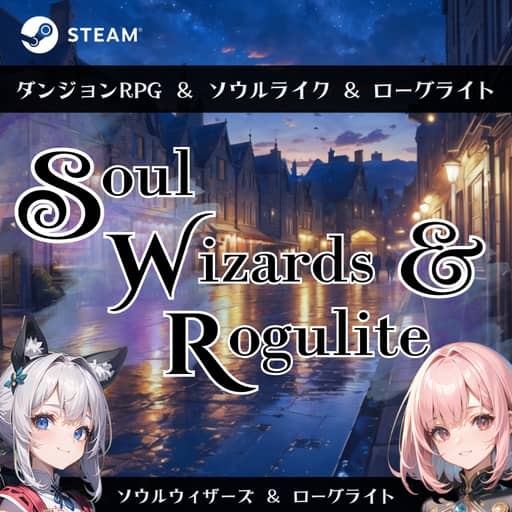























































233万年±17万年前→・チンパンジーと人類(ヒト族)の分岐
487万年±23万年前→
・ゴリラ亜科とヒト亜科の分岐
656万年±26万年前→
・ヒト科が
オランウータン亜科とヒト亜科
1300万年前→
・ヒト上科が
テナガザル科とヒト科へ分岐
2000万年前→
内村直之著「われら以外の人類」p.50より